041中台遺跡における竪穴建物の形態変化
鶴岡 英一
遺跡所在地
惣社
時代
弥生時代終末期(古墳時代早期)
中台(なかで)遺跡は上総国分僧寺跡と同一地に位置し、東日本最古の古墳といわれる神門(ごうど)古墳群を残した人びとの母村と捉えられています。
遺跡の主体となる弥生時代終末期(古墳時代早期)は、ちょうど倭国女王卑弥呼が生きた時代と重なることから、「邪馬台国時代」とも呼ばれます。遺跡からは、北陸や近畿、東海など、他地域の特徴をもつ土器が多く出土し、地域の中心的な役割を果たしていたことが考えられます。

中台遺跡周辺の航空写真(中央左上の森が国分寺、右上が市原市役所)
遺跡からは、弥生時代後期(中葉から後葉)から古墳時代前期にかけての竪穴建物跡が350棟見つかりましたが、これらを平面形態の違いから「楕円形(小判形)・胴張隅丸方形・隅丸方形・方形」の4つに分類・集計して、時期ごとにどのような特徴や変化が見られるのかを調べてみました。
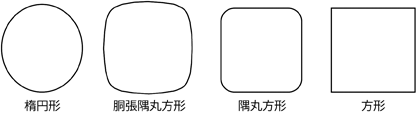
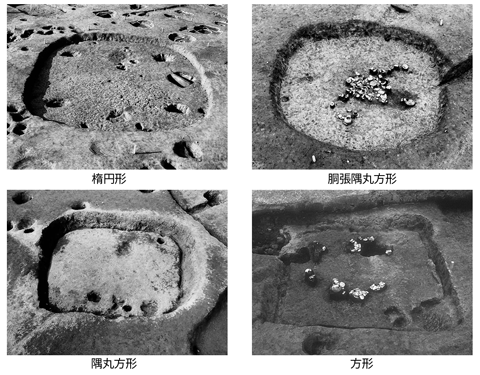
形態分類模式図と代表的な事例
下のグラフは、平面形態ごとの遺構数を時期別に集計したものです。弥生時代後期(中葉から後葉)は楕円形が圧倒的に多く、これに胴張隅丸が次いで円形を基本とすることがわかります。
弥生時代終末期(古墳時代早期)には胴張隅丸方形と隅丸方形が主体となり、ほぼ拮抗します。また、楕円形が減少する一方で、後期には見られなかった方形が出現しはじめます。
古墳時代前期には圧倒的に方形が多く、楕円形は全く見られなくなります。
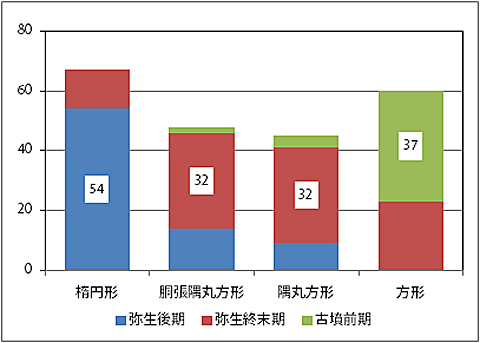
平面形態・時期別の遺構数
竪穴形態の方形化の傾向は、弥生時代終末期(古墳時代早期)にあっても、特に後半期(中台2式)に顕著であることから、この頃に最も活発化する遠隔地間交流の影響で、他地域の住居形態が取り込まれたことによると考えられます。

中台遺跡出土の外来系土器
参考文献
市原市教育委員会 2013年 『市原市中台遺跡』
大村 直 2010年 「土器の移動と移住」 『房総の考古学』 史館終刊記念 株式会社六一書房
この記事に関するお問い合わせ先
市原市埋蔵文化財調査センター
〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地
電話:0436-41-9000
ファックス:0436-42-0133
メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp
休所日:土曜日・日曜日・祝日





更新日:2022年04月18日