菅原孝標の女の更級いちはら紀行 島穴神社の路1
島穴駅をしのぶ 2006年07月29日
現在の島野一帯を、古代の「島穴郷」(しまあなのごう)に推定する説があります。島穴郷には街道中継施設の「駅」が置かれていましたが、駅路(メインルート)とともに所在地は不明です。姉崎神社と島穴神社を結ぶ小径がメインルートを示すのではないか、と指摘する説があります。
大化の改新後、律令国家の交通政策として駅制が制度化されます。官道には「駅」と呼ばれる中継エリアが整備され、公使に用いるための馬も複数飼われていました。駅には「駅家」(えきか)という公務を執り行う役所施設が置かれました。駅の運営責任者は国司ですが、実務の監督は駅長がおこないます。このポストは裕福で才覚ある人民から選ばれることが多かったようです。
 (菅原孝標の女)駅家?私が東海道を旅した11世紀前葉には、まったく無くなってましたよ。
(菅原孝標の女)駅家?私が東海道を旅した11世紀前葉には、まったく無くなってましたよ。
 (なるみ)やっぱり?駅制は律令制がゆるんだ平安時代からだんだん機能しなくなったようね。
(なるみ)やっぱり?駅制は律令制がゆるんだ平安時代からだんだん機能しなくなったようね。
はたして昔、このあたりには島穴駅家があったんでしょうか? どこに眠っているのでしょうか。
 (菅原孝標の女)ロマンをかき立てられますね。
(菅原孝標の女)ロマンをかき立てられますね。

1-1(上)小径の始点となるT字路から上り(五井)の方角を眺める。畦路の先でルートは途切れています。たび重なる養老川の移動により、主要街道が海側に廻されたため消滅したのでしょうか。とにかく、旅はこの地点から再開することにします。

1-2(左)同地点から下り方向を眺める。ここから入る島状の微高地は七ツ町と呼ばれ、集落が広がっています。

2(右)古道は人々の生活道路です。
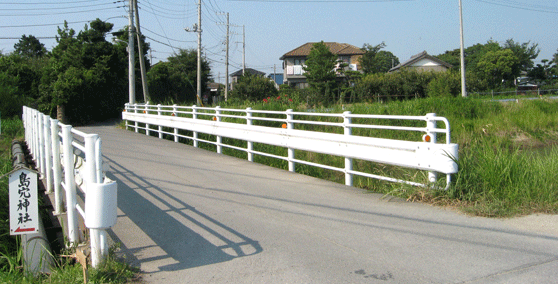
3-1(上)七ツ町を抜け水路を渡り、振り返る。七ツ町は方一町程度の微高地であることから、島穴駅家の跡と考える人もいます。実際はどうなのでしょうか。詳しいことはわかっていません。
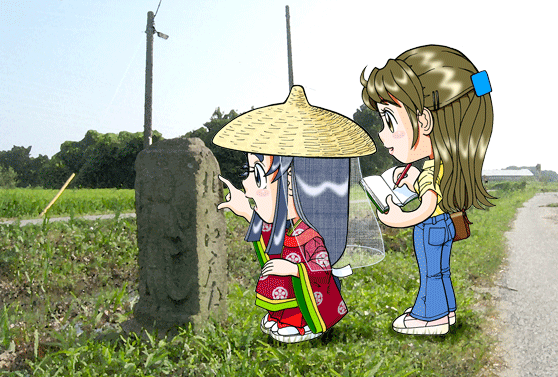
3-2(上)七ツ町から二本目の水路脇に、江戸時代の道標が立ちます。角柱形の重厚な造りで、明和2年(1765年)の造立です。正面には馬頭観音像が彫り出され、「東国分寺 嶋野村」とあります。他の面には「北ハ江戸道」「西ハあねさき道」「南ハうしく道」と彫られています。
 (菅原孝標の女)うわ、道標がある。正面の像は?
(菅原孝標の女)うわ、道標がある。正面の像は?
 (なるみ)馬頭観音よ。このように信仰の対象となる像などに道しるべを付けたものを「道標銘」(どうひょうめい)と呼んでるの。
(なるみ)馬頭観音よ。このように信仰の対象となる像などに道しるべを付けたものを「道標銘」(どうひょうめい)と呼んでるの。
 (菅原孝標の女)いつごろのものなの?
(菅原孝標の女)いつごろのものなの?
 (なるみ)江戸時代よ。交通量が大幅に増えたのでしょうね。現在遺る道しるべのほとんどが、江戸時代以降に造られてるのよ。
(なるみ)江戸時代よ。交通量が大幅に増えたのでしょうね。現在遺る道しるべのほとんどが、江戸時代以降に造られてるのよ。

3-3(左)少し進むと見通しが良くなります。昔の雰囲気を今に遺すルートだと思うのですが、いかがでしょうか。自転車で訪れると気持ちが良いです。

 (菅原孝標の女・なるみ)次はいよいよ島穴神社を訪ねます。
(菅原孝標の女・なるみ)次はいよいよ島穴神社を訪ねます。
この記事に関するお問い合わせ先
市原歴史博物館
〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地
電話:0436-41-9344
ファックス:0436-42-0133
メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp
開館時間:9時00分~17時00分
休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始





更新日:2022年04月18日