菅原孝標の女の更級いちはら紀行 姉崎神社の路4
宮山遺跡の発掘調査 1986年12月01日~1986年12月27日

姉崎神社の境内地は「宮山遺跡」(みやまいせき)として知られています。
昭和60年(1985年)に社殿が焼失しましたので、再建予定部分の380平方メートルを財団法人市原市文化財センターが発掘調査しました。
その結果、弥生時代から古墳時代終末期にかけての竪穴住居跡10軒や、中世前半期の掘立柱建物跡3棟などが発見されました。
 (さとし学芸員)こんにちは。さとし学芸員です。
(さとし学芸員)こんにちは。さとし学芸員です。
 (菅原孝標の女)おっきな凹みがたくさんありますね。
(菅原孝標の女)おっきな凹みがたくさんありますね。
これが「たてあなじゅうきょ」ですか?
 (なるみ)地面に穴を掘って、上に屋根をのせた建物の跡よ。
(なるみ)地面に穴を掘って、上に屋根をのせた建物の跡よ。
建築部材は腐って無くなっちゃうから、地面の穴だけ発見されるわけ。
 (菅原孝標の女)私、知ってる。
(菅原孝標の女)私、知ってる。
私の時代でも、身分の低い人たちは、このような家屋で暮らしてたわよ。

上 古墳時代の竪穴住居模型
手前側の茅葺きを外し、中が見えるようにしています。
 (さとし学芸員)キミの時代の竪穴住居跡は例が少なくてね、房総ではさほど多くない。
(さとし学芸員)キミの時代の竪穴住居跡は例が少なくてね、房総ではさほど多くない。
比較的裕福な人は平地式の住居に住むようになっていて、発掘調査で発見しづらいせいなのかも。
あるいは人々の住居が広範囲に散るようになって、対象地域の限られた発掘調査では発見しにくいのかもしれない。
とにかく、どういう階層の人がどのような住居で暮らしていたのか、11世紀はよくわからない時代なんだ。
まあ、平安時代の中ごろくらいまでは、普通の人はおおむね竪穴住居に住んでいたようだね。

上 宮山遺跡で発見された竪穴建物跡(弥生時代後期)
火を焚いた炉の跡が、焼けて変色しています。
 (なるみ)この遺跡の竪穴住居跡は、弥生時代が最古なんですね。
(なるみ)この遺跡の竪穴住居跡は、弥生時代が最古なんですね。
 (さとし学芸員)弥生時代でも後期初頭に絞られるようだ。
(さとし学芸員)弥生時代でも後期初頭に絞られるようだ。
久ヶ原式と呼ばれる土器の古い段階のものが発見されているよ。
 (菅原孝標の女)弥生時代の住居跡って、楕円形ですね
(菅原孝標の女)弥生時代の住居跡って、楕円形ですね

上 宮山遺跡で発見された竪穴住居跡(古墳時代後期)
 (菅原孝標の女)こちらの住居跡は四角いわね。
(菅原孝標の女)こちらの住居跡は四角いわね。
 (なるみ)古墳時代の住居跡よ。
(なるみ)古墳時代の住居跡よ。
 (さとし学芸員)この遺跡では、古墳時代の前期末から終末期前半までムラが営まれていたようだね。
(さとし学芸員)この遺跡では、古墳時代の前期末から終末期前半までムラが営まれていたようだね。
 (菅原孝標の女)奈良・平安時代の住居は?
(菅原孝標の女)奈良・平安時代の住居は?
 (さとし学芸員)発見されていないよ。
(さとし学芸員)発見されていないよ。
 (なるみ)姉崎神社が造られたので、住居は境内から押し出されたのかしら?
(なるみ)姉崎神社が造られたので、住居は境内から押し出されたのかしら?
 (さとし学芸員)そうかもね。
(さとし学芸員)そうかもね。
調査範囲が狭いから、はっきりしたことはわからないけれど。
 (菅原孝標の女)古代の姉崎神社に関わる痕跡は発見されたのかしら?
(菅原孝標の女)古代の姉崎神社に関わる痕跡は発見されたのかしら?
 (さとし学芸員)この調査では、残念ながら見つけることができなかった。
(さとし学芸員)この調査では、残念ながら見つけることができなかった。
 (なるみ)鎌倉時代になると掘立柱建物が建てられたようですね。
(なるみ)鎌倉時代になると掘立柱建物が建てられたようですね。
 (菅原孝標の女)姉崎神社に関係する建物かしら?
(菅原孝標の女)姉崎神社に関係する建物かしら?
 (さとし学芸員)たぶんね。
(さとし学芸員)たぶんね。

上 宮山遺跡で発見されたカワラケ(小皿 鎌倉時代)
 (なるみ)カワラケと呼ばれる土器の小皿が見つかっていますね。
(なるみ)カワラケと呼ばれる土器の小皿が見つかっていますね。
 (菅原孝標の女)カワラケなら、私もなじみ深いわよ。
(菅原孝標の女)カワラケなら、私もなじみ深いわよ。
でも、なんだか感じが違うわねえ。都で宴会とかに出してたのは、何か、こう、手作りっぽい感じのやつだったわよ。
 (さとし学芸員)都のカワラケは手でこねて作った手捏土器(てづくねどき)だからね。
(さとし学芸員)都のカワラケは手でこねて作った手捏土器(てづくねどき)だからね。
関東では普通、ロクロで形作ったカワラケを使っていた。もちろんこの遺跡の例もそうだよ。
東国では、手捏カワラケは、よほどのハレの場でしか使わなかったんじゃないかな。
 (菅原孝標の女)都風の特別な器なんだ。手捏は。
(菅原孝標の女)都風の特別な器なんだ。手捏は。
 (なるみ)ということは、関東で見つかるカワラケはロクロ作りが主で、重要な遺跡に少量の手捏カワラケが入ってくるわけですね。
(なるみ)ということは、関東で見つかるカワラケはロクロ作りが主で、重要な遺跡に少量の手捏カワラケが入ってくるわけですね。
 (さとし学芸員)ところが房総半島では、全くと言っていいほど手捏が入ってこないんだ。
(さとし学芸員)ところが房総半島では、全くと言っていいほど手捏が入ってこないんだ。
 (なるみ)平忠常やら上総氏やら、やたらに独立的な豪族領主が君臨した地域ですからね。
(なるみ)平忠常やら上総氏やら、やたらに独立的な豪族領主が君臨した地域ですからね。
あえて都風の食器を使わなかったのかしら。
 (さとし学芸員)全く見つからないことには、何かしらの意味があるのだろうね。
(さとし学芸員)全く見つからないことには、何かしらの意味があるのだろうね。
さて、この遺跡のカワラケは、数えていないから総量がかわからないけれど、一定量はあるようだよね。
中世の人が宴会を開く場合、使い捨て容器としてカワラケを使ったんだ。
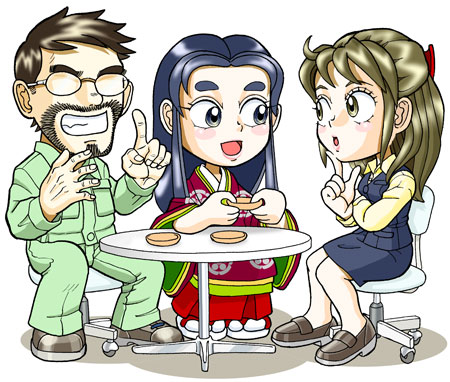
 (なるみ)この遺跡でも宴会が行われていたと?
(なるみ)この遺跡でも宴会が行われていたと?
 (さとし学芸員)わからないけれど、可能性はあるんじゃないか。
(さとし学芸員)わからないけれど、可能性はあるんじゃないか。
中世の宴会は政治的な意味が大きかったんだ。階級・階層のちがう人同士が、お互いの主従関係を確認しあう場だったのだね。
 (菅原孝標の女)宴会が開かれる代表的な場所って、領主の館ですよね。
(菅原孝標の女)宴会が開かれる代表的な場所って、領主の館ですよね。
 (さとし学芸員)領主館での宴会は、地方では鎌倉時代後期から盛んになるようだ。
(さとし学芸員)領主館での宴会は、地方では鎌倉時代後期から盛んになるようだ。
しかしそれより以前は、むしろ寺社で盛んだったとする説がある。
神仏と人との関係を確認する意味で宴会が行われたのではないか、というわけだ。
 (なるみ)なるほど。鎌倉時代は、姉?神社でもカワラケを使った饗宴があったのかもしれませんね。この遺跡から見つかったカワラケも時代的に合いますし。
(なるみ)なるほど。鎌倉時代は、姉?神社でもカワラケを使った饗宴があったのかもしれませんね。この遺跡から見つかったカワラケも時代的に合いますし。
 (さとし学芸員)同じような可能性のある例として、市内には片又木遺跡や上総国分僧寺跡が挙げられるね。
(さとし学芸員)同じような可能性のある例として、市内には片又木遺跡や上総国分僧寺跡が挙げられるね。

 (菅原孝標の女・なるみ)次回は姉崎神社境内の隣にある巨大前方後円墳、釈迦山古墳を見学します。ぜひ見てくださいね
(菅原孝標の女・なるみ)次回は姉崎神社境内の隣にある巨大前方後円墳、釈迦山古墳を見学します。ぜひ見てくださいね
この記事に関するお問い合わせ先
市原歴史博物館
〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地
電話:0436-41-9344
ファックス:0436-42-0133
メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp
開館時間:9時00分~17時00分
休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始





更新日:2022年04月18日