菅原孝標の女の更級いちはら紀行 下総国境~八幡・五所3
飯香岡八幡宮 2006年7月29日
![]() (菅原孝標の女)ああ…暑いですねえ。お宮で少し休憩しましょうよ。
(菅原孝標の女)ああ…暑いですねえ。お宮で少し休憩しましょうよ。
![]() (なるみ)賛成っ!
(なるみ)賛成っ!
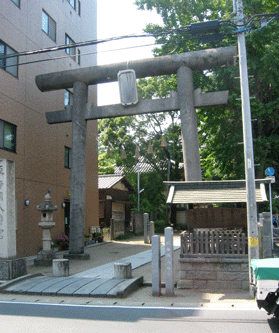
4-1(上) 飯香岡八幡宮の鳥居です。これは街道に面した参道を写したものですが、表の参道は海側に面しています。

4-2(上) こちらが海側から見た表参道です。

杜にはヤマトタマムシが…
当宮は中世の文献に出てくる「市原八幡宮」の系譜を引くと考えられています。市原八幡宮は当初、「市原別宮」と呼ばれ、平安後期から末期に石清水八幡宮の別宮として勧請されました。孝標の女の没後、数十年内くらいの成立と考えられます。別宮領は鎌倉時代以降は市原荘に発展し、宮も荘園鎮守として信仰を集めますが、国府との関係も強く、室町期には上総一宮の機能も分有したようで、社殿造営のため、棟別銭や一国平均役が賦課されています。

4-3(上) 参側の参道奥には見事な手水鉢があり、夏でも冷たい水をたたえています。寛文2年(1662)、門前町の檀那衆が奉納したものです。

4-4(上) 拝殿は元禄4年(1691)の建物で、県の文化財に指定されています。この裏に本殿があります。
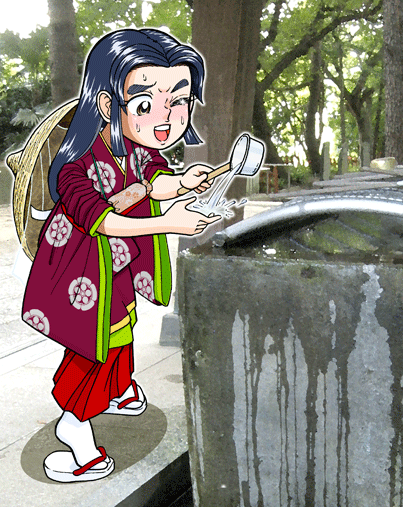

4-5(上) 本殿。室町末期の建物で、国の重要文化財に指定されています。大きく力強い印象です。上写真の拝殿とは、弊殿と呼ばれる渡り廊下状の建物でつながっています。

4-6(上) 境内の隅には浅間塚があります。一辺15メートル、高さ3.5メートルほどの四角錐状の高まりで、浅間神社を祀ります。このマウンドは、古墳を再利用したのでしょうか。もしそうなら、砂堆上の古墳として貴重です。

4-7(上) ご神木の大イチョウは「夫婦銀杏」と呼ばれ、県の天然記念物に指定されています。白鳳3年(675)に勅使桜町季満が手植えしたとの伝承があります。地元の人は「陰陽合抱樹」と呼んだそうです。この銀杏は葛飾北斎によって描かれ、『北斎漫画七編』に収録されていますが、北斎自身は現物を見ていないようで、絵はかなり樹形が異なります。
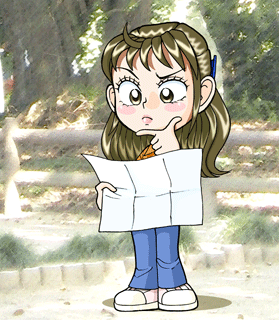

4-8(上) 境内地には様々な社が並びます。

4-9(上) 社殿をはさみ反対側にも、源頼朝が逆さに植えて戦勝祈願したと伝えられる大銀杏があります。
![]() (なるみ)喧噪な市街に社叢があると、なんだかホッとするわ。暑さもやわらぐし。
(なるみ)喧噪な市街に社叢があると、なんだかホッとするわ。暑さもやわらぐし。
![]() (菅原孝標の女)えっへん。エアコンばかりが納涼術ではないのですよ。境内を散歩して、たくさんの社を目にしました。私の先祖、菅原道真を祀る「天神宮」も見つけちゃいました(左上4-8)。
(菅原孝標の女)えっへん。エアコンばかりが納涼術ではないのですよ。境内を散歩して、たくさんの社を目にしました。私の先祖、菅原道真を祀る「天神宮」も見つけちゃいました(左上4-8)。
![]() (菅原孝標の女)
(菅原孝標の女)![]() (なるみ)次回は五所の街道集落を通ります。またお付き合いくださいね。
(なるみ)次回は五所の街道集落を通ります。またお付き合いくださいね。
この記事に関するお問い合わせ先
市原歴史博物館
〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地
電話:0436-41-9344
ファックス:0436-42-0133
メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp
開館時間:9時00分~17時00分
休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始





更新日:2022年04月18日