菅原孝標の女の更級いちはら紀行 君塚~五井2
五井 2006年7月29日
平安時代の五井は、閑散とした海岸地帯だったと思われます。古くは「武松」と呼ばれたものが、刀工宗近が五基の井戸水で名刀を鍛えたため、「五井」と呼ばれるようになった、という伝承があります。近世になると、養老川の河口が付近に移動し、陸上・水上交通の結節点として栄えました。八幡・姉崎とならび、「海岸三町」と称される継立場です。

5-1(上) 出入り口の街道を鉤状に曲げるのは近世町場の特徴。ここは入口にあたります。クランク部分に小祠が置かれています。

5-2(上) 小祠の中には六地蔵石幢が祀られています。江戸前期くらいのものでしょうか。小祠は昭和23年(1498)の道路拡張後に建てられたものです。住民に守り継がれる素朴な信仰がうかがえます。

6(上) 小街道筋に町屋が並ぶ昔ながらの景観。ちょっとレトロな建物もちらほら残ります。

7-1(上) JR五井駅。内房線のほか、小湊鉄道の始発駅でもあります。市原市はベットタウンなので、朝夕は通勤客で混雑します。

小湊鉄道 パンタグラフの付かないディーゼル車です

![]() (菅原孝標の女)小湊鉄道の車両を見つけました。かわいいですね。これに乗った養老渓谷の旅も情緒があっていいなあ。
(菅原孝標の女)小湊鉄道の車両を見つけました。かわいいですね。これに乗った養老渓谷の旅も情緒があっていいなあ。
![]() (なるみ)構内には大正14年開通時に輸入された蒸気機関車が眠ってるのよ。カッコいいでしょ! 県の文化財に指定されてます。
(なるみ)構内には大正14年開通時に輸入された蒸気機関車が眠ってるのよ。カッコいいでしょ! 県の文化財に指定されてます。



![]() (なるみ)ちょっと寄道して東口に出ましょう。国分寺台方面に延びるまっすぐな道があるの。その名も「更級通り」。
(なるみ)ちょっと寄道して東口に出ましょう。国分寺台方面に延びるまっすぐな道があるの。その名も「更級通り」。
![]() (菅原孝標の女)え?ひょっとして私の『更級日記』から命名されてるわけ?
(菅原孝標の女)え?ひょっとして私の『更級日記』から命名されてるわけ?
![]() (なるみ)中央分離帯の像はだれでしょう?
(なるみ)中央分離帯の像はだれでしょう?
![]() (菅原孝標の女)うわ、私じゃないですか。しかも美人。私の等身像なんて、日本全国探しても、これだけなんじゃないかしら。
(菅原孝標の女)うわ、私じゃないですか。しかも美人。私の等身像なんて、日本全国探しても、これだけなんじゃないかしら。
この道は現代に造られたものだから、私とは何の関わりもないのだけど、ちょっぴりうれしいなあ。
![]() (なるみ)あと数百年もすれば、この地にあなたの伝承が生まれるかもね。
(なるみ)あと数百年もすれば、この地にあなたの伝承が生まれるかもね。
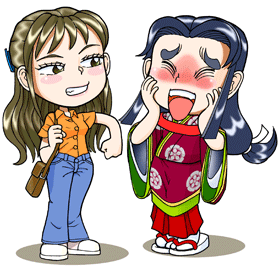
この記事に関するお問い合わせ先
市原歴史博物館
〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地
電話:0436-41-9344
ファックス:0436-42-0133
メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp
開館時間:9時00分~17時00分
休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始





更新日:2022年04月18日