菅原孝標の女の更級いちはら紀行 君塚~五井3
大宮神社(五井)から養老川に出る 2006年7月29日
五井の継場を抜けた所に大宮神社が鎮座しています。
日本武尊が東征のおりに祀ったことが始まりと伝えられています。また、この神社にも源頼朝伝説があります。さらに戦国時代の天文年間には、北条氏直が里見氏に対する勝利を祈願し、大刀を奉納したと伝えられています。
大宮神社の源頼朝伝説
「頼朝が上総を通過した際、当社に立ち寄り、戦勝祈願のため幣帛(へいはく)を奉じた。建久年間以降、頼朝は家人に命じ、しばしば報賽した。」

9-1(上) 街道に面した鳥居。

9-2(右) 参道はこれとは別に、街道にも継場にも臨まない南東方向に向いているので、神社が継場形成以前から存在した証しなのかもしれません。正面の建物は拝殿です。

9-3(上) 拝殿裏には本殿があります。
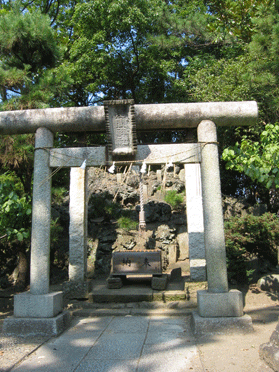
9-4(上) 境内には径8メートル、高さ2.5メートルほどの塚があり、浅間神社が祀られています。ひょっとしたら古墳かもしれません。
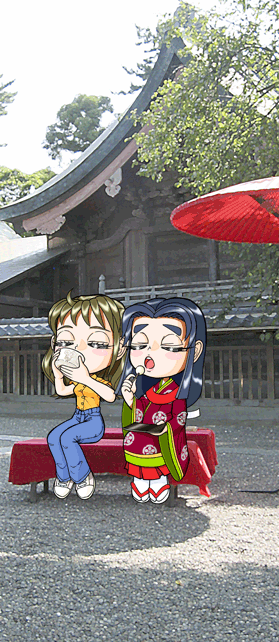
これまでとりあげてきた古代メインルート推定ラインは、房総往還におおむね沿うものと想像し、その路線を探訪してきました。しかし大宮神社より下り方面は、はっきりしたことは解りませんが、古代のルートからは外れるものと思います。古代ルートが次回以降に紹介する島野七ツ町公民館前の道路に継承されているとすれば、大宮神社からそこまでほぼ直線を通っていたのかもしれません。

10(上) 現在の養老川下流と養老大橋。養老川下流は古来から流路を変更してきました。古くは青柳側を流れていたものが、江戸時代に五井側へ移動したようです。流路が安定しないためか橋は造られず、人々は渡し船で行き来していました。明治18年(1885)に初めて木造欄干付きの「養老橋」が造られ、大変便利になりました。当時は渡橋料として金5厘を徴収したそうです。その後何度か付け替えられ、現在の「養老大橋」に生まれ変わっています。
![]()
![]() (菅原孝標の女)(なるみ)次は島穴神社と旧養老川に向かいます。
(菅原孝標の女)(なるみ)次は島穴神社と旧養老川に向かいます。
この記事に関するお問い合わせ先
市原歴史博物館
〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地
電話:0436-41-9344
ファックス:0436-42-0133
メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp
開館時間:9時00分~17時00分
休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始





更新日:2022年04月18日