貝刃(西広貝塚)
貝刃(かいじん)
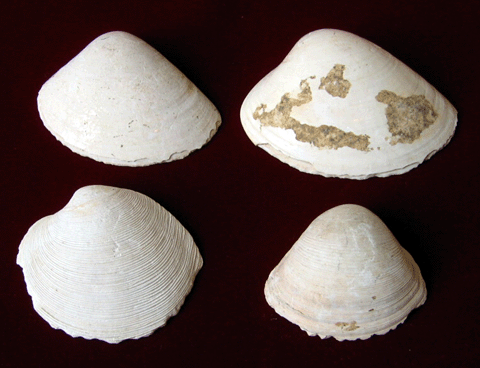
出土地
西広貝塚(さいひろかいづか)
遺跡所在地
国分寺台・西広(こくぶんじだい・さいひろ)
遺構
貝層中など
時代
縄文時代後期
解説
大型のハマグリの腹縁部(貝殻のへりの部分)への刃の付け方には、腹縁部全面におよぶもの・中央部だけのもの・片側だけによるものなど様々ですが、握りやすい比較的大型の貝殻が選ばれていることに共通性が見られます。また、貝殻の外側に刃を付けたものが主流ですが、内側に刃を付けたものもまれに見られます。今から40年ほど前に初めて発見され、それ以降、東北・関東地方など各地で大量にみつかるようになりました。貝塚からは、最も多く見つかる遺物の一つで、大きな貝塚だと数100点、時には1,000点以上見つかることがあります。食べたあとのハマグリの貝殻を主に使っていることから、道具の素材は身近にたくさんあるわけです。「使い捨て」のような感覚で作られ、捨てられたものと思われます。
ところで、この道具の用途については、魚のウロコ落とし・解体のためのものと考えられています。実験的に魚のウロコ落としをしてみたところ、刃を付けないものよりかなり効率的であったという報告があります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市原市埋蔵文化財調査センター
〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地
電話:0436-41-9000
ファックス:0436-42-0133
メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp
休所日:土曜日・日曜日・祝日





更新日:2022年04月18日