ノート027樫の木の丸太を割る【考古】
研究ノート
近藤 敏
昔から樫(カシ)の木は堅い木とされ、道具の材料として利用されました。一本の木から伐られて、丸太となった材木を半分に裂くこと(半裁)を、製材作業として実験してみました。

秋の里山の樫の木(上の写真右端)は常緑樹なので、葉はまだ青々しています。いっぽう、奥の方のコナラの木は落葉樹なので、赤く紅葉して葉を散らしています。
この山は、里山と呼ばれる農村集落の裏山になっています。1960年代の前半までは松の茂る里山でしたが、売却時皆伐されはげ山になりました。その後40年間放置されて、コナラやシラカシ、スダジイ、イタヤカエデが自然に生育し、林床の明るい場所はササ類が山を覆いました。
カシは、コナラ属アカガシ亜属に分類され、今回実験に使用したのはシラカシです。現在、関東地方南部ではよく見かけるカシの代表です。遺跡から出土する植物遺体から切片を採取して実体顕微鏡で同定作業をすると、樹木幹の細胞構造からアカガシ亜属までは同定できます。さらに、現在ではイチイカシの同定も可能になってきました。
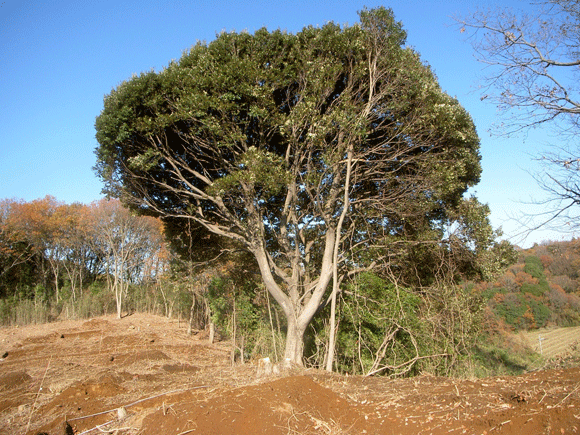
樫(カシ)の木は大きくなるものは高さ10メートル以上あります。森では木は枝を広げて葉をたくさんつけて陽を多く受けるようにします。幹は地上から1メートル~2メートルは真っ直ぐ立って、良い素材の丸太材になります。それを半裁して製材し、素材の板材を制作します。
右手前の細くて白く伸びた木も樫の木で、陽を受ける為に、高く伸びて葉をつけています。このように細く長く伸びたカシの幹は、道具の柄や棒、柱などの構造材として利用されます。


半裁実験に使用した樫の木(シラカシ)の幹の立ち株です。伐採には、チェーンソーを使用しました。


割る樫の木の大きさは、直径25センチメートル、長さ105センチメートルのほぼ円筒形です。2010年11月に伐採した、直立した約2メートル分の根側の約1メートルの部分です。
丸太割りの作業は、1月から始めました。丸太は2か月ほど放置したので、やや乾いて堅くなっています。
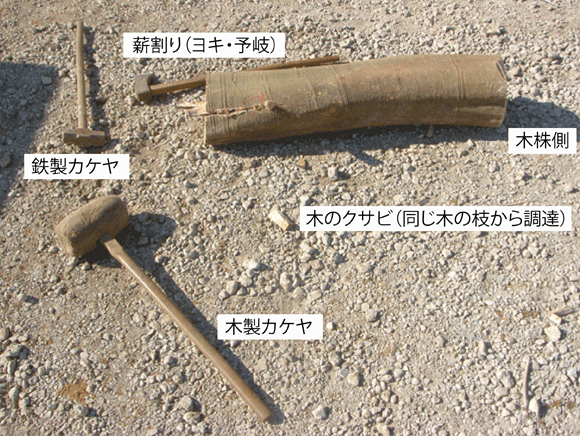
- 同じカシの木の枝からクサビを作って丸太の小口(天側)に当てたが、刺すことができず、クサビが挫けてつぶれてしまいました。そのため、最初の割れ口に鉄製の薪割り(予岐・ヨキ2850グラム)を当てて、鉄製のカケヤで叩き、丸太の小口(根側)に割れ口を作りました。薪割りは刃先の断面形状が、貝のハマグリのように丸みを帯びているため、一度目は、突き刺さりますが、2度目は樹木の反発で押し戻され抜けてきます。そこへ同じカシ材のクサビを入れて、さらに押し広げました。


- そこにカシ材のクサビを入れて、木製のカケヤで叩いてクサビを差し入れたところです。両方から打ち入れられたクサビは、裂かれる木の反発で締め付けられて、抜けない状態です。


- 木のクサビを入れると丸太に裂け目のひびが入ります。そこへ2×3センチメートル位の鉄製のクサビを入れて木が裂ける方向を導きます。裂けるひびには細身の刃先のヨキでひびを広げて、さらに薪割りヨキでさらに広げます。大きく裂かれたら、幹に木のクサビを打ち込みます。


- 最後まで裏表、左右交互に木のクサビを打ち込み、カシの木裂くことができました。しかし、裂けましたが、木の繊維がからみついて、分割ができない状況です。

シラカシ丸太を半裁するために使用した道具の全て


- 細身のヨキで繊維を切断して、最後に半裁されたシラカシの丸太です。
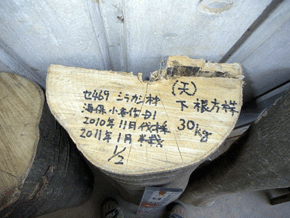
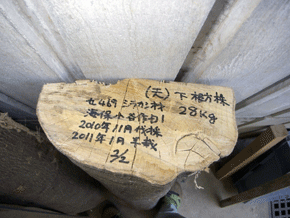
半分に裂かれた丸太の計量したところ、1/2(写真左)は30キログラムと、2/2(写真右)は28キログラムありました。
今回実験で行った、丸太割(シラカシの半裁)作業の順番
- 刃物の打ち込み、細身の予岐(ヨキ1090グラム)で天方向から小口に切れ目を入れる。
- 小口の切れ目に薪割りのハマグリ刃形状の予岐を打ち入れて、大きな裂け目にする。
- 大きな裂け目に、同じシラカシの枝材のクサビ(楔・箭)を打ち入れる。
- 小口の裂け目から両側に裂け目のひびが入るので、そこへ鉄製の小型のクサビを入れる。
- 木製のクサビの打ち入れで、裂けた部分に順次1.から4.を繰り返す作業を行う。
- 天側から地側株まで割れてきた裂け目に、最後に株側小口から予岐を打ち入れる。
- 半裁丸太の繊維の絡みを切断するために、細身の予岐を切り入れて完全に分離する。
今回シラカシ材長さ3尺(1メートル5センチメートル)余り、直径7寸5分(25センチメートル)程の約60キログラムの丸太を、半分に割る作業の実験をしましたが、大人2名で通算3時間程度作業でした。よく木材の性状を知り、作業に慣れて、道具が揃っていたならば、恐らくさらに早い作業時間で済むことでしょう。
伐採された丸太や製材された木材は、そのまま野ざらしにしますと、乾燥して締まって堅くなるようです。そのため、伐採された丸太はその場で製材加工(荒割り)されて、山から持ち出された可能性があります。その後も容易に加工するためには水に漬けて、乾燥を防ぐ方が良いようです。
立ち木を丸太にする伐採実験は、当ホームページの研究ノート「磨製石斧と鉄斧の切れ味」で報告しています。こちらも併せてご覧ください。
参考文献
- 成田寿一郎 1991年「四、木工作業および木工品の変遷40ページ~109ページ」『木の匠-木工の技術史』鹿島出版
- 山田昌久2001年「木製品の製作技術」『ものづくりの考古学』大田区立郷土博物館 東京美術
- 樋上 昇 2010年「第V章木材・木製遺品の生産と流通218ページ~240ページ」『木製品から考える地域社会』株式会社雄山閣
この記事に関するお問い合わせ先
市原歴史博物館
〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地
電話:0436-41-9344
ファックス:0436-42-0133
メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp
開館時間:9時00分~17時00分
休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始














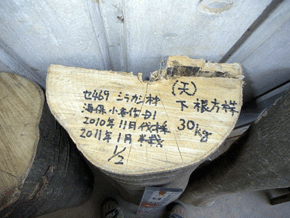
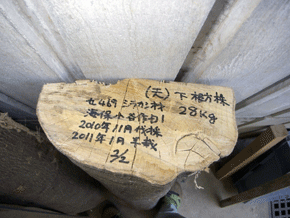
更新日:2022年04月18日