なるみのイチオシ番外編
東海の血を引く市原の弥生土器
弥生時代前期、関東地方はまだ縄文文化が根づいていました。しかし弥生文化の影響も徐々に強まっていったようで、市原市武士遺跡からは東海地方から運ばれた前期弥生土器が発見されています。
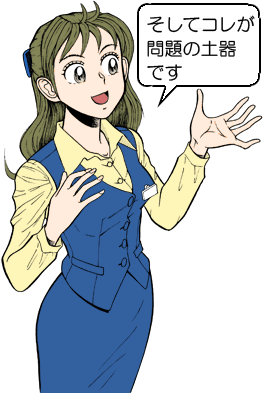

樫王式(かしおうしき)土器と言います。荒海式期ごろの縄文晩期集落に持ち込まれたものです。弥生土器が入ってくるのだから、穀物とか、けっこう手広く栽培してたんでしょうね…
全体をイメージするとこんな壺になります
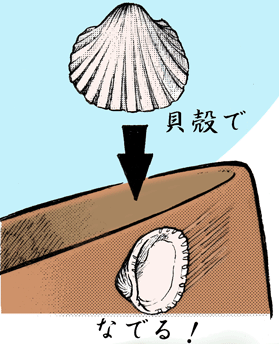

東海地方弥生土器の特徴
表面にスジが入る土器が多いみたい。このスジ、貝殻で付けているので、「貝殻条痕文」(かいがらじょうこんもん)と言うそうです。縄文時代から使われている文様なので、東海の弥生人は縄文文化の伝統を受け継いでいたと言えそうかしら?
市原市唐沢遺跡の東海系土器
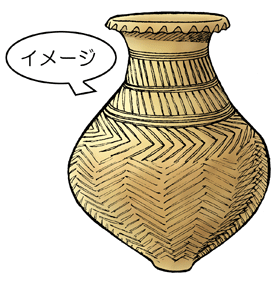
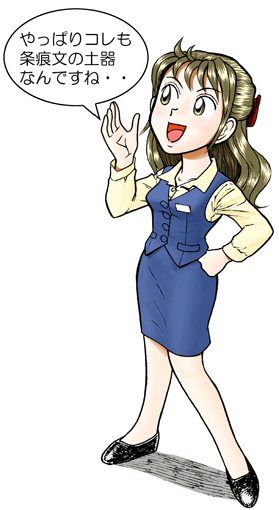
ようやく関東に集約的農耕が普及しつつあった弥生時代中期初頭でも、やはり東海の影響を色濃く受けた壺が唐沢遺跡から発見されています。
市原市域に息づいた弥生土器(須和田式土器)
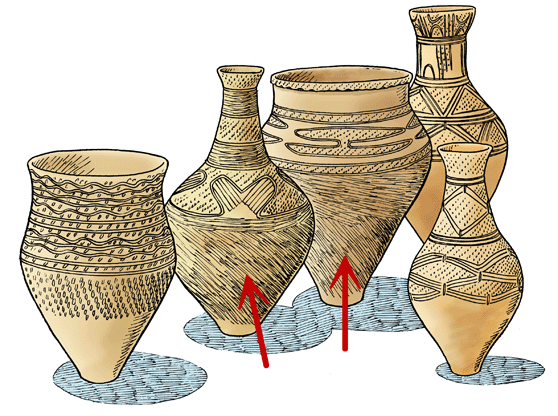
弥生時代中期、ようやく市原市域で弥生土器が作られるようになりますが、条痕文を使ったものが多いと思います。東海の血を引いてるのでしょうね、やっぱり。くらしを代表するアイテムがそうなのですから、弥生文化自体も、主に東海から伝播したのでしょうか。
ちなみにこのイラストは県内各地の須和田式土器を適当にチョイスしたもので、一括出土したものではありません。須和田ファミリーについては、次回のレポートを見てください。
この記事に関するお問い合わせ先
市原歴史博物館
〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地
電話:0436-41-9344
ファックス:0436-42-0133
メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp
開館時間:9時00分~17時00分
休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始





更新日:2022年04月18日