032市原でもみつかっていた「貝輪づくりの道具」
忍澤成視
遺跡所在地
根田(国分寺台中央)
時代
縄文時代
1 はじめに
2012年3月、待望の新刊普及誌「貝のアクセサリーづくり教室」『体験☆埋文講座』1を刊行しました。この本には、「貝輪」やペンダントなど房総半島や伊豆諸島特有の貝を使ったアクセサリーの作り方や材料の集め方を、縄文人になったつもりで解説してあります。この本の中にもふれていますが、東日本には貝輪の材料となるベンケイガイなどが多くとれる場所近くに、「貝輪づくり」を専門的におこなっていたとみられるムラがいくつか知られています。千葉県には銚子の近くに「余山(よやま)貝塚」という遺跡があり、貝輪の素材貝や加工途中のもの、途中で破損した残骸などが多量にみつかったことから、「貝輪づくりのムラ」としてかなり昔から知られていました。こういった遺跡から見つかった「遺物」の研究、そしてこれから述べる「貝」の研究とによって、本書はできあがりました。
2 市原での貝輪研究と「貝輪づくり教室」
市原市にはたくさんの貝塚があり、これまでに多くの遺跡が発掘調査され、遺跡や出土した遺物の研究が進められてきました。とくに、国分寺台にある「祇園原(ぎおんばら)貝塚」や「西広(さいひろ)貝塚」は、全国屈指の規模と内容を有していることから、縄文時代研究には欠かすことのできない存在として注目されています。
なかでも西広貝塚は、発掘調査後10年の歳月をかけ2007年に報告書を刊行しましたが、この遺跡からは実に3,000点の貝製装身具がみつかり関係者をはじめ多くの人を驚かせました。この数と内容は、縄文時代のものとしては間違いなく日本一のものです。そしてこのうち貝で作られた腕飾り、すなわち「貝輪」が全体のおよそ1割にあたる400点ほどみつかっており、その素材や作り方の研究がすすめられました。その研究は、単に遺物の観察だけにとどまらず、材料となった貝がどこからもたらされ、どうやって貝輪に仕上げられていったのか、房総半島や伊豆諸島をはじめあちこちの海岸に実際に出かけ、標本として現生貝(現在生きている貝)を集め、これらの観察や計測、そして多量の標本を使った製作実験を続けました。研究開始は1999年9月ですから、今から13年も前のことになります。そして、市原の資料ばかりでなく、千葉県・愛知県・石川県・宮城県・秋田県・北海道など、各地の貝輪や貝輪づくりに使われた道具類を詳しく調べた結果、縄文人がおこなっていた貝輪づくりの仕方を復元できるようになりました(忍澤2001・2005a・2006)。
そして市原では、この研究成果をもとにした「貝輪づくり教室」が2000年5月からスタートし、今では貝輪の材料集めからおこなうスタイルへと進化し、10年以上を経過した子供たちに人気の講座として定着しています(忍澤2005b)。
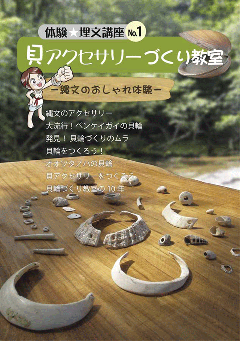
刊行された普及冊子

貝輪づくり教室の様子
3 祇園原貝塚からみつかった貝輪づくりの道具
先にふれた西広貝塚と並んで著名な遺跡である祇園原貝塚からも、数は西広貝塚には及ばないものの、計30点の貝輪がみつかっています。このうち17点がサルボウガイ・アカガイ・サトウガイなどのフネガイ科の貝、2点がオオツタノハ、1点がアカニシ、そして10点がベンケイガイです(写真01)。
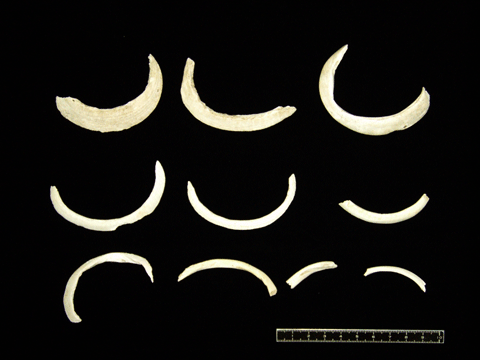
写真01 祇園原貝塚から出土した貝輪
祇園原貝塚は、西広貝塚に先行するかたちで整理作業がおこなわれ、報告書刊行は1999年の3月、貝輪研究が本格的に始まる前のことでした。したがって、ここで紹介する遺物も私の記憶の片隅に押しやられていました。その遺物とは、発掘調査報告書の中では「未詳石器」として扱い、用途のよくわからない石器として遺物の最後に掲載したものです。
1043は、3次調査・UI-42区出土で半分が欠損したもの、長さ7.0・幅4.5・厚さ2.8cm、重さ89.7g、砂岩製(古い硬い砂質堆積岩)です。1044は、2次調査・A3-42区出土で一部を欠損するもの、長さ6.2・幅5.6・厚さ5.4cm、重さ157.7g、新期砂岩製(新第三系以降のやや軟質な堆積岩)です(写真02・03)。

写真02 用途不明として報告した祇園原貝塚出土の石器(表面)

写真03 用途不明として報告した祇園原貝塚出土の石器(裏面)
両者に共通するのは、硬さや密度がやや異なるものの材質が砂岩であることと、同じように溝や突起がみられる歪(いびつ)な形態をし、手のひらに収まるほどの大きさである点です(写真04)。報告書を刊行した時点では、この「かたち」が意図的に作られたものではないかと考えたため、用途にたどり着くことができずに「未詳石器」としてしまいました。現在では、この形態の石器は、貝輪づくりをおこなっていたムラで多くみつかる特徴的な遺物として知られています。秋田県能代市「柏子所(かしこどころ)貝塚」、宮城県東松島市「里浜(さとはま)貝塚」、千葉県銚子市「余山(よやま)貝塚」からは複数の個体が発見されています。

写真04 溝や突起をもち、いびつなかたちをした石器
それではその用途とは何でしょうか。写真05を見てください。上段が未使用の石、下段があることに使ったあとの石です。いずれも砂岩製の石で、手のひらにすっぽり収まる大きさのものです。答えは貝輪づくりの際、石のハンマーであけた穴の周囲をこすってさらに穴を大きく広げるため、そしてさらに穴の周囲や貝殻の表面を入念にこすって貝輪を完成させるための「砥石」です(写真06)。写真05下段は、子供たちが一生懸命に長時間作業した結果、石の周囲がすり減ってしまったものです。溝が深くなると磨きにくいため、磨く場所を隣に移しているうち、段々と凸凹の歪な形態になってしまったのです。

写真05 上段 未使用の石 下段 使ったあとの石

写真06 砂岩製の砥石を使った貝輪づくり
ここで今一度、祇園原貝塚からみつかったベンケイガイ製の貝輪をよく観察してみましょう。貝にあけられた穴の周囲や貝殻表面の加工の度合いは一様ではなく、段階的に完成品に近づけられていく工程を追うことができます(写真07)。つぎに、祇園原貝塚からみつかったこの石器と貝輪を見てください(写真08)。貝輪の縁のカーブと石器に残された使用痕のカーブがよく合致し、この石が貝輪づくりの仕上げ用に使われた砥石であることがよくわかります。
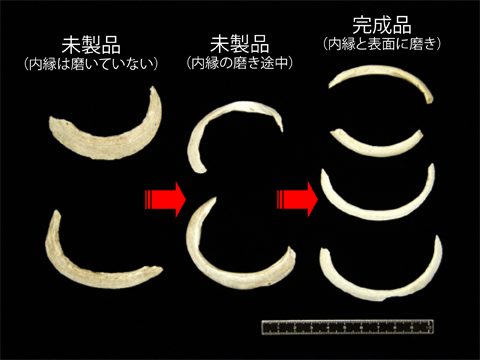
写真07 貝輪の製作工程

写真08 祇園原貝塚から出土した貝輪と砥石
4 祇園原貝塚の資料からわかること
祇園原貝塚の2点の石器は、貝輪づくり用の道具であることがわかりました。出土した貝輪にも製作途中のものから完成品までみられることから、貝輪の仕上げ加工が祇園原ムラの中でおこなわれていたことを示しており、そのための道具が見つかっていたことは重要な発見です。
これまで、このような歪(いびつ)な形態の砥石は、貝輪生産遺跡以外ではあまりみつかっていませんでした。貝輪生産遺跡からみつかるのは、貝輪残骸や貝輪未製品がほとんどであることから、砥石を使ったある程度の仕上げはするものの、多くは完成品の手前の段階で「出荷」されたのではと考えられてきました。今回の発見は、これを裏付けるものです。腕の周りや手首の大きさには個人差があります。未製品の状態で生産地から取り寄せたものを、それぞれのムラでムラの人たちに合う大きさに仕上げたほうが効率的で、しかも自分にぴったりで好みにあう貝輪に仕上げることができます。
ところで、現在貝輪づくり教室で使用している砥石の原石は、銚子の犬吠埼(いぬぼうさき)近くの海岸までわざわざ出かけて拾い集めてきたものです(写真09・10)。この海岸の石は、砥石素材として良好なものであることが知られており、余山貝塚から貝輪とともにみつかっている砥石の素材もこのあたりの石を使っていると思われます。ここの石が砥石に適しているのは、比較的硬い砂岩が多く、ベンケイガイの硬い貝殻に負けない硬さと緻密さをもっているからです。貝輪づくり教室では、かつては市販の砥石を使っていましたが、この時には石のほうが簡単にすり減ってしまってなかなか貝輪ができあがらない状態でした。現在では銚子産の砥石を使っているため、以前とは比較にならないほど短時間で貝輪を仕上げられるようになりました。

写真09 銚子市犬吠崎近くの海岸

写真10 良好な砥石素材
砥石原石の産地同定は無理かもしれませんが、もしかしたら祇園原貝塚の2つの砥石は、ベンケイガイとともに貝輪づくり用の「キット」として運ばれてきたものかもしれません(写真11)。
これらの遺物が示していることの奥深さは、祇園原貝塚の報告書を刊行した15年前には気づきもしませんでした。それを思うと、研究の進展を感じずにはいられません。
市原での貝輪づくり研究の成果を、是非一度、普及誌「貝のアクセサリーづくり教室」『体験☆埋文講座』No1にてご覧いただければ幸いです。

写真11 祇園原貝塚出土の貝輪づくりキット
参考文献
- 忍澤成視 2001 「縄文時代における主要貝輪素材ベンケイガイの研究」『史館』31
- 忍澤成視 2005a 「貝輪素材として選択された貝種流行の背景-フネガイ科製の貝輪素材の分析を中心として-」『動物考古学』22
- 忍澤成視 2005b 「ベンケイガイ製貝輪に学ぶ-体験学習としての「貝輪づくり」-」『財団法人市原市文化財センター研究紀要』5
- 忍澤成視 2006 「縄文時代におけるベンケイガイ製貝輪生産-現生打ち上げ貝調査を基礎とした成果-」『動物考古学』23
この記事に関するお問い合わせ先
市原市埋蔵文化財調査センター
〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地
電話:0436-41-9000
ファックス:0436-42-0133
メール:bunkazai-center@city.ichihara.lg.jp
休所日:土曜日・日曜日・祝日





更新日:2022年04月18日