ノート007三和・東海地区の縄文遺跡【考古】
研究ノート
忍澤成視
はじめに
ほぼ市域の中央を南北に流れる養老川とその支流が開析した台地上には、数多くの縄文時代の遺跡が知られています。養老川の中流から下流にかけての地域には、その左岸(西側)と右岸(東側)の両方に遺跡が存在します。今回は、三和・東海地区にある遺跡のうち、これまでに何らかの調査が行われているものについて、その概要と成果の一部を紹介します。

図1 養老川中流域から村田川にかけての縄文時代主要遺跡
- 分目貝塚
- 諸久蔵貝塚
- 大道遺跡
- 山見塚遺跡
- 北旭台遺跡
- 山ノ神遺跡
- 武士遺跡
- 山倉堂谷貝塚
- 山倉天王貝塚
- 山倉貝塚
- 西広貝塚
- 草刈貝塚
養老川中流域左岸
分目貝塚(図1 No.1)
市原市の埋蔵文化財地図では、宮原字布谷台と分目字堂谷に所在する地点貝塚を併せて分目貝塚として扱っています(市原市教育委員会1988)。両者の間は南北にのびる小支谷で分断されています。平成4年、市道112号線建設にともなう確認調査がおこなわれ、このうちの宮原字布谷台にある貝塚のほうを、宮原布谷台貝塚として発掘調査しました。遺跡は、標高24メートルほどの台地上に位置し、貝塚はこの台地上と東端の崖面にも及んでいることがわかりました。とくに、東端の貝層の一部は低地の水田下にまで広がっていることもわかり、貝層の厚さは1メートルを超えるものもあるとみられています。確認調査であるため、部分的な発掘のみによる所見ですが、住居跡や貝層の時期は中期であることが判明しています(米田1996)。市道はまだ建設されておらず、現地は発掘調査後も現況をとどめています。
諸久蔵貝塚(図1 No.2)
諸久蔵貝塚は海保字諸久蔵に所在し、標高60mほどの台地上に立地します。東西120メートル・南北100メートルの馬蹄形を呈する大規模貝塚であることが知られています(千葉県文化財保護協会1983)。近年、この貝塚の東側隣接地は東関東自動車道が建設され、関連遺跡が発掘調査されましたが、本貝塚についてはこれまでに調査されたことはありません。遺跡の現況は、大半が杉林を中心とする山林になっており、遺跡西側の一部が果樹園として利用されこの部分では貝層が大きく削平されてしまっていますが、他の部分では保存状態は概ね良好で、特に東側の山林内では、地表を覆うスギの枯れ枝や草を除くと一面に密度の高い貝層が露呈する状態です。表面採集できる土器片から判断すると遺跡が縄文後期を主体とするものであることがわかりますが、貝層の規模からみてその前後の時期のものの存在も否定はできません。いずれにしても、このあたりでは最も保存状態のよい貝塚の一つと言えます。筆者はかつて、杉林の中で貝輪破片を表面採集しています(忍澤2005a)。
大道遺跡(図1 No.3)
大道遺跡は、今富大道に所在し、標高70メートルほどの台地上に立地します。今富と立野を結ぶ市道2135号線沿いにあり、調査はこの路線の改良工事に伴って昭和61年におこなわれました。この遺跡の西側には先述の諸久蔵貝塚が存在します。発掘調査の結果、縄文時代早期・茅山式期を主体とする多数の炉穴と多量の土器が検出されました(米田1988)。炉穴とは、この時期特有の遺構で、住居の中ではなく屋外に設けられた調理施設と考えられるものです。
山見塚遺跡(図1 No.4)
山見塚遺跡は、立野字山見塚に所在し、標高78メートルほどの台地上に立地します。前述の分目貝塚の南約2キロほどに位置します。昭和60年、ゴルフ場増設工事に伴って発掘調査されました。確認調査ではありましたが、縄文後期の環状に展開する集落の一部、規模の大きな地点貝塚、そしてこれらに伴う土器を主体とする多量の遺物が発見されました。とくに貝層中からは、ハマグリ・イボキサゴなど内湾干潟に生息する貝類やクロダイ・ボラ・マアジなどの魚類の骨、イノシシ・シカ・タヌキなど獣類の骨も検出され、当時の漁撈・狩猟・海浜部での採集など生業活動の一端の様子を垣間見るための貴重な資料が得られています(木對1987)。
養老川中流域右岸から市原台地
北旭台遺跡(図1 No.5)
北旭台遺跡は、磯ヶ谷字北旭台に所在し、標高45メートルほどの台地上に立地します。平成元年、民間のゴルフ練習場建設に伴って発掘調査されました。調査の結果、縄文時代早期から前期にかけての住居跡や炉穴・集石・陥穴などが発見されました。とくに、この時期のまとまった住居跡・集落の発見は、市内では珍しいものです。
また、北旭台遺跡は、弥生時代の南海産大型巻貝である「ゴホウラ」製貝輪を真似てつくられた「有鉤銅釧」が出土した遺跡としても有名です(木對1990)。
山ノ神遺跡(図1 No.6)
山ノ神遺跡は、福増字山ノ神に所在し、標高70メートルほどの台地上に立地します。昭和63年、民間の産業廃棄物処分場建設に伴って発掘調査されました。調査の結果、縄文早期の炉穴と中期の埋甕などがみつかりました(浅利1989)。このあたりでは、数少ない調査事例です。
武士遺跡(図1 No.7)
武士遺跡は、勝間字土器石に所在し、標高75メートルほどの台地上に立地します。字名に「土器石(かわらけいし」とあるように、地元では昔から多量の土器や石器が地表に顔を出していることで知られ、市の埋蔵文化財分布地図では「土器石遺跡」として登録されています。本遺跡が立地する幅約200メートルほどの台地上は、ほぼ全面に縄文時代の足跡が残されていると言ってもよいくらいで、千葉県水道局の市原東給水場や福増浄水場の建設に伴っておこなわれた調査では、縄文中期後半から後期中葉の大集落が発見されました。とくに、昭和62年から平成元年にかけておこなわれた台地平坦面のほぼ全域に相当するおよそ5万平方メートルにおよぶ調査では、住居跡423軒・土坑879基をはじめ膨大な数の遺構と、遺構の覆土内に形成された小規模な貝塚など、この時期の市内の遺跡としては最大規模のものであることがわかりました(加納1998)。
山倉堂谷・天王貝塚(図1 No.8・9)
山倉堂谷・天王貝塚は、山倉字堂谷・字猿子谷に所在し、標高50メートルほどの台地上に立地します。現在遺跡は、杉林や竹林などの山林内に保存されています。
平成元年、市内の重要遺跡(貝塚)の確認調査として遺跡の現況把握がおこなわれました。この調査では、市内では初めての試みとして、貝塚を掘らずにその貝層規模と分布をとらえる方法が導入されました。特殊な機器を使用し、地表から地下に向けて放射された電磁波の反射速度から、地層の変化や地中に存在する異物の存在を把握する「地下レーダー探査」という方法です。市街地での水道管やガス管など古い埋設物の探査や、エジプトでの王朝時代の地下埋設物の探査などに導入され、成果をあげています。この方法は、地下に空洞部があったり、まわりの土壌とは極めて異質のものが存在している場合にはとくに威力を発揮します。したがって、土の中に貝層が厚く堆積するような貝塚をとらえるのには有効です。従来の貝塚調査では、調査地内にいくつものトレンチ(試掘用の溝)を掘ったり、ボーリング棒を地表面からさしてその感触から貝層の有無を調べる方法がとられていました。前者の場合、一部にせよ貴重な貝塚が破壊されることになりますし、後者の場合にはボーリング棒の届かないような地中深い位置にある貝層がとらえられない可能性があります。今回の地下レーダー探査を用いた調査では、これらの欠点が補われ、貝塚がより実態に近いかたちで把握されました。
なお、地表面から採集された土器により、北側に位置する堂谷貝塚が縄文中期を主体とするもの、南側に位置する天王貝塚が縄文後期を主体とするものであることもわかりました。この貝塚は、南北250メートル・東西150メートルにおよぶ大貝塚で、平面形態はいわゆる「メガネ状」を呈しますが、これは時期の異なる2つの貝塚が連結した結果です。有名な千葉市加曽利貝塚を小規模にしたようなもので、大変珍しいものです。市内では最大規模、しかも保存状態も良好なことから、その重要性が特筆されます。
山倉貝塚(図1 No.10)
山倉貝塚は、山倉字南貝塚に所在し、標高40メートルほどの台地上に立地します。臨海工業地帯への工業用水道の水源である「山倉ダム」の一角に位置します。最近、営業を停止した「千葉県山倉こどもの国」建設に伴って、昭和43年に早稲田大学考古学研究会によって発掘調査されました。貝塚の一部は現在も保存され、こどもの国の中のバーベキュー施設のあった場所付近には、貝層の一部を地表から確認することがでました。直径約110メートルの環状を呈する貝塚で、調査は北側のA地区と南側のB地区でおこなわれました。ハマグリ・イボキサゴ主体の厚さ50センチメートルから1メートルほどの貝層で、時期は中期後半から後期中頃までのものでした。貝層の下からは、住居跡や土坑、多数の埋葬人骨も発見されました(図2 忍澤2000)。市内では数少ない中期主体の貝塚として非常に貴重な遺跡です。遺物等は現在、早稲田大学考古学研究室に保管されています。
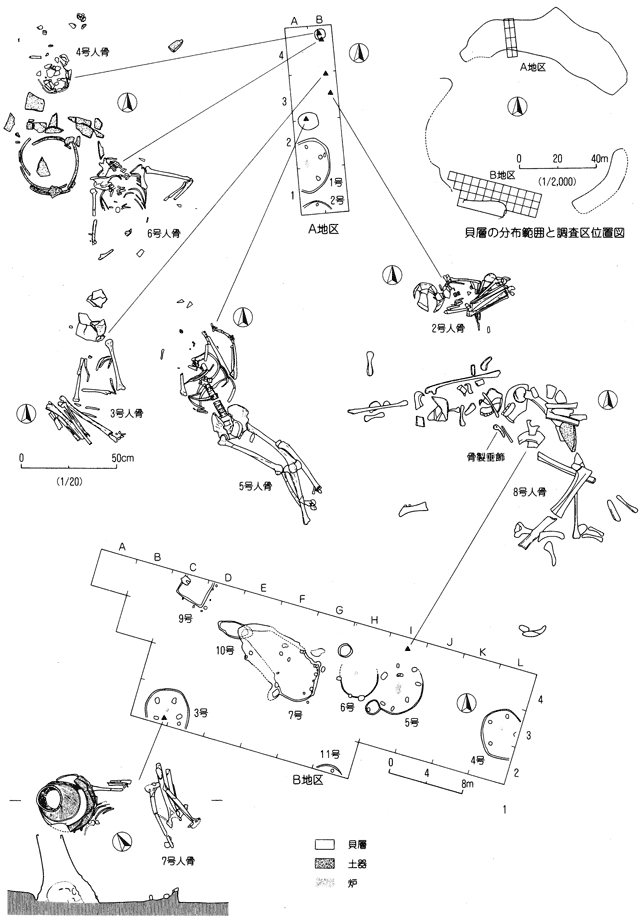
図2 山倉貝塚貝層分布図および遺構配置と人骨出土状況
ところで、筆者は最近、昭和43年の調査に先行しておこなわれた、昭和23年の上総国分寺周辺遺跡群の総合調査で発掘された資料の一部を見る機会を得ました(西村1949)。そして、この調査で出土したタカラガイの加工品が、伊豆諸島産の大変珍しいもの(ヤクシマダカラ)であることをつきとめました。同様の資料が、直線距離で北に6キロメートルほど離れた市内ちはら台に所在する草刈貝塚(図1 No.12)からも出土していることが判明したことから、同時期に存在した二つのムラに何らかの交流があったことが推定できました(忍澤2005b)。
西広貝塚(図1 No.11)
千葉市との境界を流れる村田川と養老川に挟まれたいわゆる市原台地上に形成された貝塚で、この台地上には後述する山倉貝塚・祇園原貝塚をはじめ大小の貝塚が多く存在します。遺跡は標高43メートルほどの台地上に立地します。貝塚の規模は、南北150メートル・東西120メートルほど、南西側に開口部をもついわゆる馬蹄形を呈する大貝塚です(図3)。
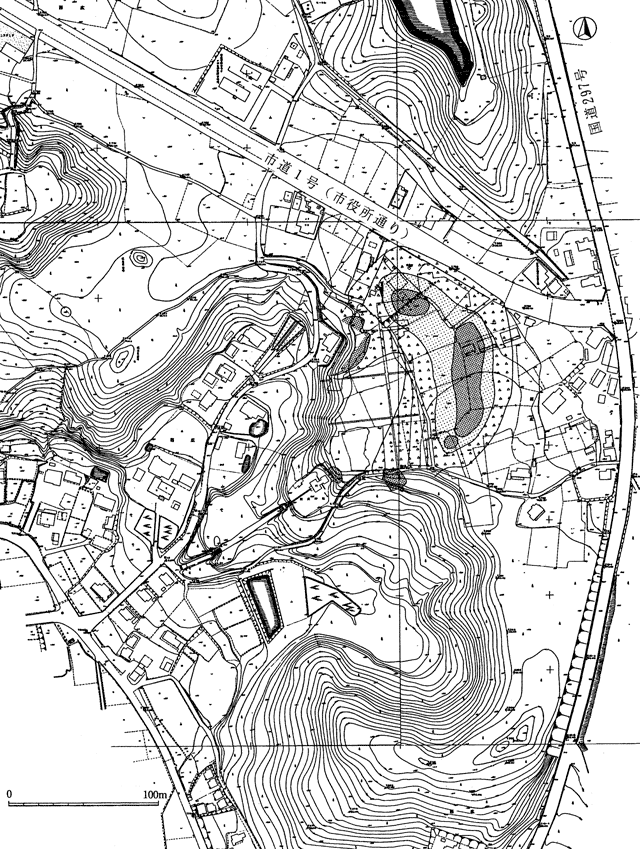
図3 西広貝塚貝層分布
この貝塚の名前は、祇園原貝塚と並んで全国的にみても大変有名です。発掘調査中に明らかとなった遺構や遺物の内容が注目されたためです。祇園原貝塚は、中央広場を取り囲むように展開された縄文後期各時期のムラのあり方や、しっかりとした出入り口施設をもつ特徴的な形態の多数の住居跡、そして100体を超える埋葬人骨で構成される墓域の存在がとくに注目されました(忍澤1999)。一方、西広貝塚は、祇園原と同じように展開する縄文後期のムラや多数の埋葬人骨群も目を引きますが(米田1977)、ムラの西側の斜面部に形成された最大2メートルにおよぶ厚い貝層の調査が最も有名になりました。また、関東地方では大変珍しい、縄文晩期中頃の貝塚が発掘されたことでも有名です。西側の斜面貝層の発掘には、およそ1年の歳月を要しましたが、その後の貝層内容物の分析作業にはさらに膨大な歳月と労力を要しました。発掘調査は、国分寺台土地区画整理事業に伴い、昭和47年の第1次調査から昭和62年の7次調査まで断続的におこなわれました。遺跡はほぼ全域が発掘調査され、今は現地で貝塚の面影を知ることはできません。旧地盤は削平され、現在住宅地がある地盤は旧況からかなり下がったレベルとなっています。平成9年からは本格的な整理作業が開始され、その成果の一部が平成17年に公表されています(安井ほか2005)。そして、平成19年3月、ついに最終報告書が刊行されます。整理作業開始から10年、最初の報告書刊行から実に30年という歳月が流れたことになります。
これほどの整理期間を要したのは、多数の遺構や土器・石器などの遺物が多量に出土したこともありますが、最大2メートルの厚さの斜面貝層部分を中心に、貝塚の貝層の全てを遺跡から持ち帰り、その内容物の分析を行ったからです。分析した貝層サンプル量は、整理箱にしておよそ3万箱におよびました。貝層をフルイの上で水洗いし、残った人工遺物(土器・石器・土製品・骨角貝製品など)、貝類の殻、魚・獣類の骨を全て抽出し種の同定作業・計数・集計するのに5年を要しました。しかし、この作業は決して無駄ではなく、この結果これまで全国のどこの貝塚でもわからなかった、縄文時代の狩猟・漁撈・採集など生業活動の詳細な内容が、捕獲対象となった動物の遺骸の分析によって明らかとなり、また微細な人工遺物の徹底した回収作業によって、その捕獲技術の一部についても明らかにすることができました。さらに、土・石・貝製の装身具が多量に抽出でき、特に貝製の腕輪・ペンダントなどはその種類・数は間違いなく日本一です。これらからは、縄文時代の装身習俗の実態と、房総半島を中心におこなわれていた装身具素材としての貝類(とくにタカラガイ・イモガイなど南房総産のもの)をめぐる交易活動実態が明らかになりつつあります(忍澤2001)。西広貝塚の調査成果が投げかける問題は多様であり、今年度末の報告書刊行後、日本の縄文文化研究の進展に寄与するであろうことは間違いありません。来年度以降、いろいろなかたちでその成果をお披露目したいと思っています。どうぞ、みなさんも大いに御期待ください。
<市原市地方史研究連絡協議会 2006年 『市原市東海・海上・三和地区の遺跡と文化財』より転載・一部改変>
参考文献
- 財団法人市原市文化財センター 1989年 『福増山ノ神遺跡』
- 市原市教育委員会 1988年 『市原市埋蔵文化財分布地図−北部編−』
- 財団法人市原市文化財センター 1994年 『市原市文化財センター年報 平成元年度』
- 市原市教育委員会 1999年 『上総国分寺台遺跡調査報告』V
- 忍澤成視 2000年 「山倉貝塚」 財団法人千葉県史料研究財団 2000年 『千葉県の歴史』資料編考古1 所収
- 忍澤成視 2001年 「千葉県西広貝塚出土のタカラガイ加工品」 国立歴史民俗博物館 2001年 『動物考古』16号 所収
- 忍澤成視 2005a 「諸久蔵貝塚採集の貝輪」 財団法人市原市文化財センター 2005年 『市原市文化財センター研究紀要』V 所収
- 忍澤成視 2005b 「タカラガイ加工品の用途を示す一事例」 国立歴史民俗博物館 2005年 『動物考古学』22号 所収。
- 財団法人千葉県文化財センター 1997年『武士遺跡2』
- 財団法人市原市文化財センター 1987年 『外迎山遺跡・唐沢遺跡・山見塚遺跡』
- 財団法人市原市文化財センター 1990年 『市原市北旭台遺跡』
- 千葉県文化財保護協会 1983年 『千葉県の貝塚−千葉県所在貝塚遺跡詳細分布調査報告書−』
- 千葉県教育委員会 1949年 『山倉貝塚』
- 市原市教育委員会 2005年 『市原市西広貝塚II』
- 市原市教育委員会 1977年 『西広貝塚』
- 財団法人市原市文化財センター 1988年 『今富大道遺跡』
- 財団法人市原市文化財センター 1996年 『市原市文化財センター年報 平成4年度』
この記事に関するお問い合わせ先
市原歴史博物館
〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地
電話:0436-41-9344
ファックス:0436-42-0133
メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp
開館時間:9時00分~17時00分
休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始





更新日:2022年04月18日