ノート002市原市の環濠集落【考古】
研究ノート
大村直
弥生時代は、「倭国乱れ、相攻伐して年を歴たり」といった中国史書の記事にもみられるように、列島規模の政治体制をつくりあげた古墳時代に向かって飛躍をとげた時代であり、ムラの周囲に堅固な溝をめぐらした環濠集落は、弥生時代を代表する遺跡であるといわれています。一時期マスコミに大きく取り上げられた、佐賀県吉野ヶ里遺跡や奈良県唐古・鍵遺跡の、幾重にもめぐらされた濠や、復元された物見櫓は、激動の時代を強烈に印象づけるものとなりました。
しかし、環濠集落は、北九州や近畿地方に限られた集落形態ではありません。現状では太平洋岸地域で、現在の利根川流域まで分布を広げています。南関東地方において、環濠集落ないし環濠に特徴的な断面V字溝が検出された遺跡は、管見によるだけでも178遺跡を数え、千葉県下ではこの内42遺跡が所在します。中でも、市原市域の環濠集落は、現状で13遺跡において検出されており、弥生時代中期後半(西暦紀元前50〜紀元後50年頃)の南関東地方では、神奈川県鶴見川流域、東京都荒川流域とともに、濃密な分布を形成しています。
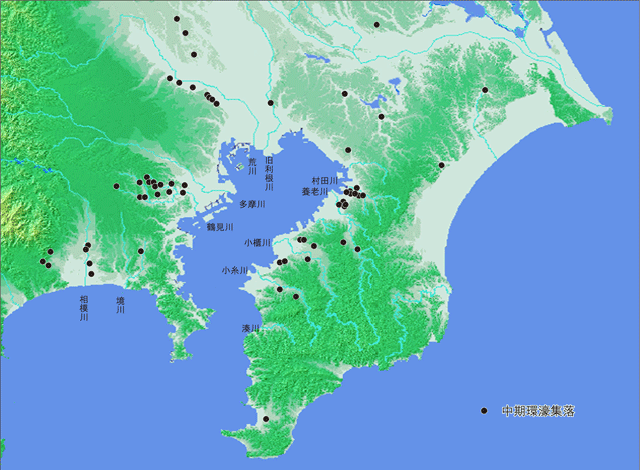
南関東地方環濠集落分布図
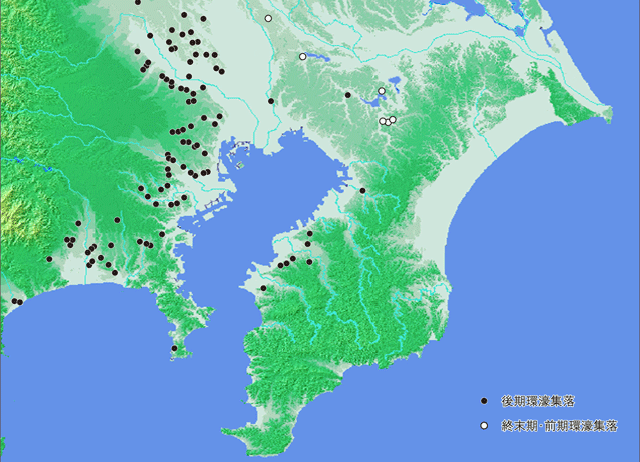
南関東地方環濠集落分布図
南関東地方では、おおむね本格的な農耕集落の形成と同時に環濠の開削が始まりました。市原市域の環濠集落は、村田川下流域、養老川下流域右岸、養老川中流域に分布上のまとまりが認められます。とくに、国分寺台地区の根田代遺跡、台遺跡、向原台遺跡、菊間地区の菊間遺跡、菊間深道遺跡、菊間手永遺跡、大厩地区の大厩遺跡、大厩浅間様古墳下層遺跡(大厩遺跡群)など、近接して環濠集落「群」を形成しています。この時期は、東京湾岸平野部に直接面する台地縁辺部への集落の進出が認められ、さらに、姉崎地区の砂堆上や、養老川や村田川の低位段丘面など低地部での遺跡の検出例も増加しつつあります。これは、沖積地に対する積極的な水田開発によるものと考えられ、菊間手永遺跡に近接する市原条里制遺跡では、弥生時代中期後半の土器を多量に出土した自然流路と、極小区画水田多数が検出されました。水田範囲は、実信地区、並木地区、仮称県立スタジアム地区をあわせ、北東−南西方向550メートル、北西−南東方向350メートルにおよんでいます。水田開発にともなう大規模な労働投下を、環濠集落への集住の一要因としてとらえることも可能であると思われます。
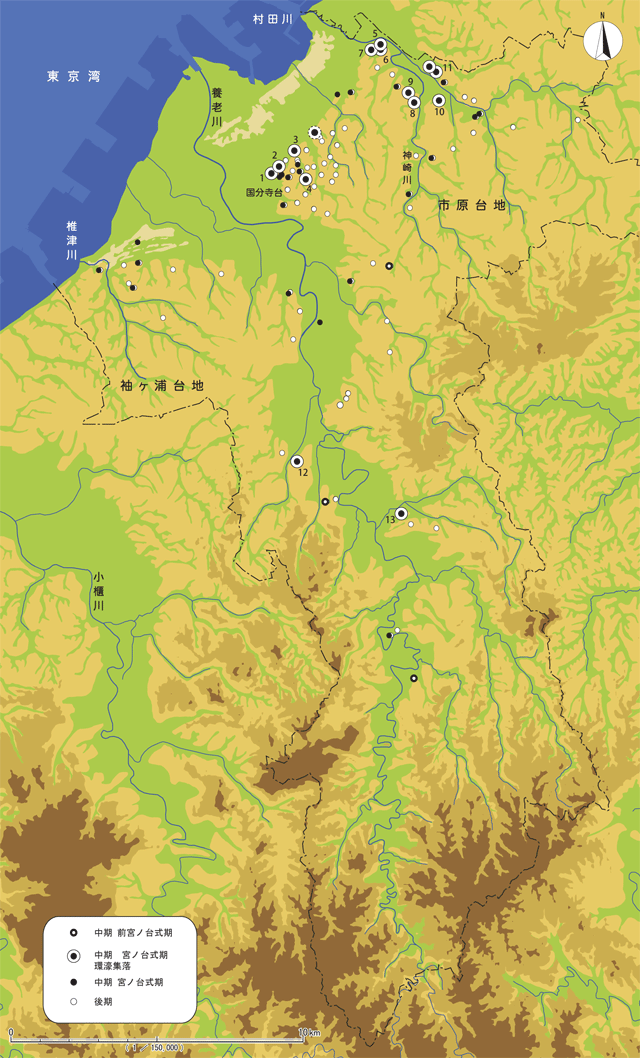
市原市域の弥生時代中後期集落
| 市町村 | 遺跡名 | 時期 |
|---|---|---|
| 野田市 | 二ッ塚殿台遺跡 | 終末前期初 |
| 柏市 | 戸張一番割遺跡 | 終末前期初 |
| 市川市 | 国府台遺跡 | 中期/後期 |
| 市川市 | 須和田遺跡 | 後期 |
| 多古町 | 柏熊遺跡 | 中期/後期 |
| 佐倉市 | 大崎台遺跡 | 中期/末前初(条濠) |
| 佐倉市 | 高岡大山遺跡 | 終末前期初 |
| 佐倉市 | 石川阿ら地遺跡 | 終末前期初 |
| 印西市 | 向ノ地遺跡 | 終末前期初 |
| 八千代市 | 田原窪遺跡 | 中期 |
| 八千代市 | 道地遺跡 | 後期 |
| 千葉市 | 戸張作遺跡 | 中期 |
| 東金市 | 道庭遺跡 | 中期 |
| 市原市11 | 草刈遺跡 | 中期/後期(条濠) |
| 市原市5 | 菊間遺跡 | 中期 |
| 市原市6 | 菊間深道遺跡 | 中期 |
| 市原市7 | 菊間手永遺跡 | 中期 |
| 市原市8 | 大厩遺跡 | 中期 |
| 市原市9 | 大厩浅間様古墳下層 | 中期 |
| 市原市10 | 潤井戸西山遺跡(草刈尾梨遺跡) | 中期 |
| 市原市2 | 向原台遺跡 | 中期 |
| 市原市1 | 根田代遺跡 | 中期 |
| 市原市2 | 台遺跡C地点 | 中期 |
| 市原市4 | 祇園原貝塚上層 | 中期 |
| 市原市12 | 南岩崎遺跡 | 中期 |
| 市原市13 | 南総中学遺跡 | 中期 |
| 袖ヶ浦市 | 美生遺跡第4地点 | 後期 |
| 袖ヶ浦市 | 西ノ窪遺跡 | 中期 |
| 袖ヶ浦市 | 根形台遺跡群16地点 | |
| 袖ヶ浦市 | 根形台遺跡群4地点(堂野遺跡) | 中期 |
| 袖ヶ浦市 | 根形台遺跡群14地点(関野遺跡) | 後期 |
| 袖ヶ浦市 | 根形台遺跡群1・3地点(境No.2遺跡) | 中期 |
| 袖ヶ浦市 | 西原遺跡 | 中期 |
| 袖ヶ浦市 | 滝ノ口向台遺跡 | 中期/後期 |
| 木更津市 | 東谷遺跡 | 後期 |
| 木更津市 | 鹿島塚A遺跡(庚申塚B遺跡) | 中期/後期 |
| 木更津市 | 大山台遺跡 | 後期 |
| 木更津市 | 千束台遺跡 | 中期/後期 |
| 富津市 | 前三舟台遺跡 | 後期 |
| 君津市 | 鹿島台遺跡 | 中期 |
| 君津市 | 畝山遺跡 | 中期 |
| 館山市 | 萱野遺跡 | 中期 |
昨年度整理作業が完了した根田代遺跡は、市内の環濠集落では、最も内容が明らかとなった遺跡です。根田代遺跡は、養老川右岸の市原台地北西端の独立丘陵上に立地し、環濠規模は、北東−南西方向の長軸長外径で203.5メートル、北西−南東方向の短軸長で約133メートル、環濠区画総面積は約19,830平方メートルを測ります。環濠幅は調査時最大で約3メートル、本来は、幅5メートル、深さ4メートルに達していたと推定されます。環濠区画内は、残念ながら調査前に破壊が進み、全容を明らかにすることはできませんでしたが、区画内全体で70〜80軒程度の竪穴住居跡が存在したと推定されます。しかし、根田代遺跡の環濠は、長期にわたって維持されることなく、弥生時代中期終末段階には環濠内に多量の土器が投棄されています。市内の他の環濠集落も、中期後半段階を中心とし、おおむね中期末までには環濠の機能を停止していたようです。
市内には、確実に弥生時代後期と考えられる環濠集落は確認されていません。後期環濠集落は、相模湾岸から東京湾西岸の荒川流域、大宮台地に濃密な分布を形成しますが、東京湾東岸地域では、東京湾西岸と地理的接点をもつ地域に限られる傾向があります。しかし、東京湾東岸の村田川流域から小糸川流域にいたる地域では、後期において、関東地方でも有数の大規模な遺跡群を形成しました。この時期の集落は、台地上広範囲に竪穴住居跡が展開し、環濠区画内に集住する環濠集落とは異なる、開放的な集落形態をとっています。
弥生時代後期の相模湾沿岸地域、武蔵野台地における環濠集落形成の契機は、東海地方からの大規模な集団移住という具体的な事実をもって検証されつつあります。一方、東京湾東岸地域は、東海地方からの影響は希薄で、外部に対して閉鎖的で安定した社会を形成していたのかも知れません。
弥生時代は、「倭国乱」の時代と言われています。しかし、各地域における環濠集落の成立と解体は、時期、契機とも多様であり、中国史書には記されてはいない具体的な「史実」は、それぞれの地域の歴史の中で解明されなければなりません。
<第20回市原市文化財センター遺跡発表会要旨より転載・一部改変>
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市原歴史博物館
〒290-0011 千葉県市原市能満1489番地
電話:0436-41-9344
ファックス:0436-42-0133
メール:imuseum@city.ichihara.lg.jp
開館時間:9時00分~17時00分
休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始





更新日:2022年04月18日